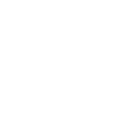医療保険に加入していれば、病気やけがなどで入院したときに入院給付金を受け取ることが可能です。入院したときに受け取れる1日あたりの入院給付金は、「入院日額」と呼びます。
入院日額を高く設定しておけば、万一の際にしっかりと備えられる一方で、保険料負担が大きくなります。無理のない範囲でリスクに備えられる入院日額を設定するためにも、まずは平均的な金額や日額別のメリット・デメリットをおさえておきましょう。
当記事では、入院日額の平均額から入院時に必要となる費用の目安、さらに入院日額をいくらに設定すべきかといった点まで詳しく説明します。
1.入院給付金日額の平均額
医療保険における入院日額とは、入院給付金の1日あたりの給付額のことです。
公益財団法人 生命保険文化センターが発表した「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」によると、入院日額の全体平均は8,700円となっていました。
とは言え、男性・女性の性別によっても設定する入院日額にはやや違いがあることも特徴です。下記に、男性・女性それぞれにおける入院日額の分布割合を紹介します。
| 金額 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 3,000円未満 | 1.3% | 2.9% |
| 3,000円~5,000円未満 | 4.0% | 7.6% |
| 5,000円~7,000円未満 | 30.4% | 38.5% |
| 7,000円~10,000円未満 | 6.2% | 6.3% |
| 10,000円~15,000円未満 | 31.9% | 26.3% |
| 15,000円以上 | 16.6% | 10.6% |
| 平均金額 | 9,600円 | 8,100円 |
出典:公益財団法人 生命保険文化センター ホームページ「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」
上記の分布を見ると、男性は「10,000~15,000円未満」の割合が最も高い一方で、女性は「5,000~7,000円未満」の割合が最も高くなっています。加えて、入院日額の平均額が該当する「7,000~10,000円未満」の割合は男女ともに6%台と、やや低いことも特徴です。
1-1.【年代別】入院給付金日額
設定する入院日額に差が生じる要素は、性別だけではありません。男女ともに、年代によっても1日あたりの入院給付金の平均額が異なることを覚えておきましょう。
| 年代 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20代 | 7,400円 | 7,100円 |
| 30代 | 9,200円 | 8,000円 |
| 40代 | 10,500円 | 8,400円 |
| 50代 | 10,900円 | 8,700円 |
| 60代 | 9,600円 | 8,300円 |
| 70代 | 8,300円 | 7,000円 |
出典:公益財団法人 生命保険文化センター ホームページ「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」
(単位:%)
※18~79歳までの男女2,550人を対象に集計
入院日額のボリュームゾーンは、男性で40代、女性で50代となります。また、男性は40~50代で10,000円以上の入院日額を受け取る傾向にある一方で、女性は全年代において7,000~8,000円台と、男性と比較して3,000円程度の差が生じていることも分かっています。これには、主に男性が一家の大黒柱を担うことが背景として挙げられるでしょう。
2.入院に必要な費用の平均額
入院日額をいくらに設定すべきか考えるときは、万が一入院した際に必要となる費用を考えることが大切です。
「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」によると、入院費用の全体平均額は19.8万円となっています。しかし、これはあくまでも全体平均額であり、入院日数によって必要な費用は大きく異なることも覚えておきましょう。
| 入院時の自己負担費用* | |
|---|---|
| 入院日数 | 平均金額 |
| 全体 | 198,000円 |
| 5日未満 | 87,000円 |
| 5~7日 | 152,000円 |
| 8~14日 | 164,000円 |
| 15~30日 | 284,000円 |
| 31~60日 | 309,000円 |
| 61日以上 | 759,000円 |
出典:公益財団法人 生命保険文化センター ホームページ「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」
入院日数が「5日未満」の場合、入院費用は10万円を満たしません。また、「5~7日」「8~14日」はさほど差がなく、入院費用の全体平均額に最も近い数値となっています。 しかし、15日間を超えてくると月をまたぎやすくなることから入院費用は跳ね上がり、30万円近くの自己負担費用が必要となる点に注意が必要です。
2-1.【疾病別】入院に必要な費用の目安
疾病によって必要な治療や入院日数は変わり、入院時に必要となる費用目安も異なります。
下記は、疾病ごとの入院費用の目安です。
| 疾病の名称 | 入院費の1日単価 | 3割負担の金額目安 |
|---|---|---|
| 胃がん | 約73,000円 | 約22,000円 |
| 直腸がん | 約88,000円 | 約26,000円 |
| 気管支・肺がん | 約96,000円 | 約29,000円 |
| 乳がん | 約95,000円 | 約29,000円 |
| 急性心筋梗塞 | 約171,000円 | 約51,000円 |
| 肺炎 | 約51,000円 | 約15,000円 |
| 喘息 | 約50,000円 | 約15,000円 |
| 脳梗塞 | 約67,000円 | 約20,000円 |
| 糖尿病 | 約42,000円 | 約13,000円 |
| 大腿骨頸部骨折 | 約70,000円 | 約21,000円 |
| 胃潰瘍 | 約60,000円 | 約18,000円 |
| 急性虫垂炎 | 約86,000円 | 約26,000円 |
| 白内障 | 約103,000円 | 約31,000円 |
| 子宮筋腫 | 約119,000円 | 約36,000円 |
| 膝関節症 | 約79,000円 | 約24,000円 |
※がんについては全ステージおよびステージ不明の内容も含めた平均値
あらゆる疾病の中でも、特に入院の費用負担が大きくなりやすいのは急性心筋梗塞です。3割負担後の金額でも5万円を超えるケースは珍しくなく、入院期間が長ければ長いほど負担は重くなるでしょう。また、がんや白内障、子宮筋腫などの高度な治療を要する疾病も同様に、自己負担額は大きくなる傾向です。
2-2.入院時に逸失する収入の平均額
入院時には入院費用を真っ先に考えがちですが、普段通りの生活が送れないことにより生じる「逸失収入」も忘れてはなりません。逸失収入とは、入院しなければ本来得られたはずの収入のことです。入院日額は、退院後の自身・家族の生活水準を大きく下げてしまわないよう、入院費用だけでなく生活費も考慮して設定する必要があります。
「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」によると、入院時の1日あたりの逸失収入は下記の通りとなっていました。
| 逸失収入 | 割合 |
|---|---|
| 5,000円未満 | 18.7% |
| 5,000~7,000円未満 | 10.8% |
| 7,000~10,000円未満 | 15.8% |
| 10,000~15,000円未満 | 19.4% |
| 15,000~20,000円未満 | 3.6% |
| 20,000~30,000円未満 | 10.8% |
| 30,000~40,000円未満 | 7.9% |
| 40,000円以上 | 12.9% |
| 平均金額 | 21,000円 |
出典:公益財団法人 生命保険文化センター ホームページ「2022(令和4)年度
生活保障に関する調査」
(単位:%)
※逸失収入があった男女139人を対象に集計
入院時の1日あたりの平均逸失収入は、21,000円です。ボリュームゾーンは10,000~15,000円と、全体の約2割を占めていることも分かります。なお、逸失収入は「本来であれば普段通りに働いて得るはずの収入」となるため、無職の方であれば収入減がないことから0円として算定されることも覚えておきましょう。
3.入院給付金の日額はいくらにすべき?
入院給付金日額を考える際は、「差額ベッド代」についてもおさえておきましょう。差額ベッド代とは、個室や2~4人部屋などの特別療養環境室に入院した場合に、健康保険の適用範囲外で請求される費用のことです。
厚生労働省が公表している「中央社会保険医療協議会 主な選定療養に係る報告状況」の資料によると、1日あたりの差額ベッド代の平均徴収額は6,613円でした。うち個室は8,315円、4人部屋は2,639円と、人数の増加に伴い差額ベッド代負担は小さくなることも見てとれます。
出典:厚生労働省ホームページ
入院の費用負担を抑えるためには、このような差額ベッド代もふまえて適切な療養環境に 加えて、疾病入院給付金の適切な日額も考えておく必要があります。入院日額を5,000円 程度・10,000円程度にするメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。
3-1.日額5,000円程度にするメリットとデメリット
入院給付日額を5,000円にする場合のメリットとデメリットは、下記の通りです。
| メリット | 保険料負担を低減させられる |
|---|---|
| デメリット | 長期入院の場合は負担分を賄いきれなくなる可能性がある |
日額を5,000円程度にする事により、毎月の保険料負担を抑えられるという点は、大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、その分入院日額も下がるため入院が長期化した場合は入院給付金だけでは賄えなくなる可能性もあり、万一の不足分をカバーできる別の対策や備えも必要となります。
3-2.日額1万円程度にするメリットとデメリット
入院給付日額を1万円程度にする場合のメリットとデメリットは、下記の通りです。
| メリット | 入院時の自己負担額を抑えられる |
|---|---|
| デメリット | 保険料負担が大きい |
1万円程度の入院日額であれば確かな保障となるため、日額5,000円と比較すると自己負担割合も大幅に抑えられます。しかし、毎月かかる保険料負担は、一般的に日額5,000円と比較して2倍となるため、リスクに備えるあまり家計を圧迫してしまわないよう注意が必要です。
3-3.入院給付金とあわせて考えたい特約
万一のリスクに備えられる入院給付金は、必ずしも入院日数分の全額を受け取れるわけではありません。医療保険の入院給付金には「支払限度日数」が設けられており、いわば上限額が定められることとなります。一度の入院で30日・60日・120日まで医療給付金を受け取れるなど、生命保険会社・保険プランによっても日数はさまざまです。
入院リスクにしっかりと備えておきたいという方は、入院給付金とあわせて「入院一時金 特約」や「女性疾病特約」を付帯することも1つの手段と言えるでしょう。それぞれの特約の概要は、下記の通りです。
| 入院一時金特約 | ・医療保険加入者が病気やけがなどで入院をしたときに、まとまった一時金を受け取れる特約 ・入院日数にかかわらず、一律で給付される |
|---|---|
| 女性疾病特約 | 女性特有の疾病で入院をしたときに、入院給付額が上乗せされる特約 |
これらの特約は、医療保険に付帯する形が基本です。特約を付帯した場合は主契約の保険料とは別に特約保険料が割増されます。保険料負担は少なからず大きくなるものの、より合理的かつニーズに合った保障を受けられるため、一度検討してみるのもよいでしょう。
まとめ
「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」によると、入院日額の全体平均は8,700円となっていました。性別によっても平均値にはやや違いがあり、女性は7,000~8,000円台と全体平均より少し低い一方で、男性は7,000~10,000円台と高めになっていることも 特徴です。
適切な入院日額を決めるためには、平均的な入院日額のほか、逸失収入の相場や自身の貯蓄状況もふまえておく必要があります。また、入院日額が高ければ高いほど、毎月の保険料負担が大きくなることも覚えておきましょう。
リスクにしっかりと備えておきたいという方は、医療保険に特約を付帯することも一案です。ここまでの内容を参考に、ぜひ自身や家族にとって最適な保険選びをしてみてください。