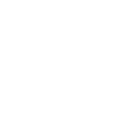養老保険の満期保険金は、受け取り方によって課税される税金の種類や金額が変わってきます。基本的には、一時金で受け取る場合は一時所得として、年金として受け取る場合は雑所得として課税されます。
本記事では、養老保険の満期保険金にかかる税金の仕組みと、受取方法による違いについて詳しく解説します。
また、確定申告での扱い方までお伝えしますので、ぜひ最後までご一読ください。
目次
養老保険の満期保険金には税金がかかる
養老保険の満期保険金は所得とみなされ、所得税か贈与税のいずれかの税金が発生します。なお、所得税だけではなく住民税も課税されますので、ご注意ください。どちらの税金として取り扱うのかは、
- 保険料を負担した人
- 満期保険金を受け取る人
の関係によって変わってきます。以下で、どのように区分されているのかを説明します。
所得税がかかる場合
保険料の負担者と満期保険金の受取人が『同一人物』である場合、所得税の課税対象です。自分で加入した養老保険の満期保険金を、自ら受け取るケースが該当します。
所得税の課税方法は、満期保険金の受け取り方によって異なり、一時金で受け取る場合は「一時所得(※1)」として、年金として受け取る場合は「雑所得(※2)」として計算します。どちらの場合も支払った保険料は控除されるため、差額のみが課税対象です。
例として、20年満期の生命保険を契約していた場合、
- 毎月の保険料:1万円(20年間で総額240万円支払い)
- 満期保険金:300万円の場合
- 300万円(受取金額) – 240万円(支払保険料) = 60万円(差額)
となり、課税対象は60万円です。
特別控除があるからと不適切に区分した場合、修正申告や追徴課税のリスクがあるため、該当したほうの所得としての正直な告知をおすすめします。
- ※1 一時所得:所得から50万円の特別控除が認められ、課税所得の計算において2分の1のみが総所得金額に算入
- ※2 雑所得:特別控除や2分の1課税の特例はなく、所得の全額が総所得金額に算入
出典:国税庁(生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm)
贈与税がかかる場合
保険料の負担者と満期保険金の『受取人が異なる場合』は、贈与税の課税対象です。例えば、親が保険料を支払い、子どもが満期保険金を受け取るようなケースが該当します。
満期保険金の受け取り方が一時金、年金のどちらでも贈与税の対象です。年金として受け取る場合は、年金を受け取る権利そのものに対して贈与税が課税されます。また、実際に受け取る年金に対し、所得税も課税される可能性があります。
出典:国税庁(生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm)
源泉徴収だけで済む場合もある
養老保険が「金融類似商品」として扱われる場合は、源泉徴収だけで課税関係が完了します。金融類似商品として扱われるのは、
- 保険期間が5年以下の場合
- 保険期間が5年超であっても5年以内に解約された場合
- 保険期間が5年以下の「一時払養老保険」等
が該当します。
この場合、満期保険金と払込保険料との差益に対して「所得税、復興特別所得税、住民税の合計」が源泉徴収され、生命保険会社から税引後の金額が支払われます。また、確定申告も不要です。
出典:生命保険文化センター(税金に関するQ&A)(https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/569.html)、国税庁(金融類似商品と税金)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1520.htm)
確定申告は不要なの?
以下では、養老保険の満期保険金における確定申告の扱いを、ケース別に説明します。
確定申告が必要なケース
満期保険金を一時金で受け取った場合、一時所得(※)として確定申告が必要です。
計算方法は、受け取った満期保険金から支払った保険料総額を差し引き、さらに特別控除として50万円まで控除できます。その後、計算結果の2分の1が課税対象です。
※一時所得:営利を目的としない活動から生じた所得で、労働や役務の対価として得た報酬ではない一時的な所得
出典:国税庁(一時所得)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm)
確定申告が不要なケース
保険期間が5年以内の一時払養老保険の場合は、源泉分離課税となり確定申告は不要です。養老保険の満期保険金は、受け取り方によって所得の種類が変わり、同時に確定申告の要否も変わってきます。
満期保険金を年金として受け取る場合、通常は雑所得として扱われ、源泉徴収の対象です。年収として支払時に、所得税および復興特別所得税が自動的に源泉徴収される仕組みが適用されます。
ただし、源泉徴収後の確定申告の必要性については、個々の状況によって異なります。例えば、雑所得の差額が一定額以上になる場合や、他の所得と合わせて基礎控除を超える場合には、確定申告が必要となるケースがあるでしょう。
次では、実際の計算方法について例題を挙げながら説明します。
出典:国税庁(保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm)
養老保険の満期保険金にかかる税金の計算方法
養老保険の満期保険金にかかる税金の金額は、受取方法によって計算方法が異なります。一括受取の場合は一時所得として、年金受取の場合は雑所得としての計算です。
以下では、それぞれの計算方法を具体例を交えて解説します。
満期保険金が「一時所得」になった場合
一時所得の計算方法は、以下の手順で行います。ここでは、総額300万円の保険料を支払い、満期時に500万円を受け取る場合を考えてみましょう。
一時所得には特別控除が50万円となるため、
- 500万円(満期保険金) – 300万円(保険料総額) – 50万円(特別控除) = 150万円(一時所得の金額)
という計算になり、課税対象は150万円になります。ただし一時所得は2分の1、つまり半分だけを課税対象とする制度のため、実際の課税対象額は『75万円』となります。
この金額を給与所得などに合算して、決められた所得税率を掛けたものが最終的に確定申告で納付する税額となります。
出典:国税庁(一時所得)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm)
満期保険金が「雑所得」になった場合
年金として受け取る場合は、雑所得として計算します。雑所得の場合は、原則として確定申告が必要となります。ただし、所得が基礎控除以下の場合は申告が不要になります。
例えば、年間300万円の年金を受け取り、その年の年金に対応する払込保険料が50万円の場合、
- 差額 = 300万円 – 50万円 = 250万円
- → 差額が25万円以上の場合は源泉徴収後に確定申告が必要となる可能性がある
となります。源泉徴収があることで複雑に感じますが、差額は振込された時点で自動徴収されている状態です。なお、計算して差額が25万円未満であっても確定申告が必要な場合があるため、注意が必要です。
出典:国税庁(生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm)
養老保険の満期保険金の受け取り方
養老保険の満期保険金は、受け取り方によって税負担が変わってきます。そして、受け取り方には、以下の3つの方法があります。
- 一括受け取り
- 年金受け取り
- 据え置き
どの受け取り方を選ぶかは、現在の収入状況、将来の収入見込み、そして保険金をいつまでに必要とするかなど、ご自身の状況から見極めるのが一般的です。ただ、そこまで詳しく計算できないという方も多いはずです。
そこで、以下では基本の受け取り方と、据え置きについて説明します。
満期保険金は一括で受け取る
基本的には、満期保険金を一括で受け取り、税務上の「一時所得」として扱いましょう。一時所得には50万円の特別控除が適用され、さらにその金額を2分の1にした額が課税対象となるためです。
この方法であれば、雑収入と比較した際、特別控除が受けられるメリットを得られます。
据え置きも活用する
満期保険金の受け取りを急ぐ必要がない場合は、据え置き(※)という選択肢も検討に値します。
据え置き期間中は保険会社が満期保険金を運用するため、利息を受け取れます。現役で働いている間は据え置いて利息を受け取り、退職後に受け取るという方法も可能です。
据え置きできるかどうかは商品によって異なり、できない場合もあります。また、据え置き期間は保険会社によって異なりますが、一般的に数年から数十年の範囲となります。
ただし、据え置き期間中の利率は変動する可能性があるため、契約時に保険会社から詳細な説明を受けることが重要です。また、毎年繰り入れられる利息は雑所得として扱われることから、所得税の申告が必要となる点にも留意してください。
※満期保険金を満期時に受け取らずそのまま置いておくこと
出典:国税庁(生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm)
まとめ
養老保険の満期保険金は、受け取り方によって課税方法や税額が変わります。一時金で受け取る場合は一時所得として、年金として受け取る場合は雑所得として課税されます。また、保険期間が5年以下の場合は源泉分離課税となり、確定申告は不要です。
すぐに資金が必要な場合を除き、自身の生活設計に合わせて受取方法を選ぶことで、長年積み立ててきた保険金を効率的に活用できます。ただし、非常に線引きや区分が難しい専門的な部分となるため、不安な場合は必要に応じて税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
よくある質問(FAQ)
満期保険金を受け取ったら必ず確定申告が必要?
満期保険金を受け取った場合の確定申告の要否は、状況によって異なります。基本的に、年間収入が2,000万円以下で、勤務先で年末調整が実施されている場合は、確定申告は不要となります。
確定申告が必要か、不要かは下表にまとめています。ただし、個人の状況によって異なる可能性があるため、参考程度に留めてください。
| 状況 | 確定申告※ | 備考 |
|---|---|---|
| 保険期間が5年以内の一時払養老保険 | × | 源泉分離課税が適用される |
| 年金として受け取る場合(差額が25万円未満) | △ | 所得が基礎控除以下の場合は申告不要 |
| 給与所得や年金収入のみで、一時所得が年間20万円以下 | △ | 特例による |
| 一時金として受け取る場合(一時所得として扱われる) | ○ | 特別控除(50万円)と2分の1課税が適用 |
| 年金として受け取る場合で、年金額から保険料を控除した差額が25万円以上 | ○ | 源泉徴収後に確定申告が必要 |
| 源泉徴収されていない満期保険金を受け取った場合 | ○ | – |
| 確定申告による所得税の還付を受けたい場合 | ○ | – |
※ ○:確定申告が必要、△:確認が必要、×:確定申告が不要
出典:生命保険文化センター(税金に関するQ&A)(https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/569.html)
「養老保険が金融類似商品になる」ってどういうこと?
養老保険が金融類似商品とみなされるのは、以下の要件に該当する場合です。
- 保険期間が5年以内の契約である
- 保険料の払い込みが5年を超える保険を5年以内に解約した場合
金融類似商品に該当すると、申告分離課税の対象となり、他の所得とは分離して税額が計算されます。この場合、満期時の受取金額(配当金を含む)と払込保険料との差益に対して税率を適用します。
通常、生命保険会社が源泉徴収を行い、税引後の金額を支払うため、受取人は確定申告をおこなう必要がありません。なお、復興特別所得税は2037年(令和19年)12月31日までの期間限定で課税されます。
出典:国税庁(申告分離課税制度)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm)