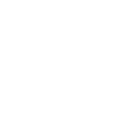一言で「医療保険」と言っても、さまざまな種類があります。公的医療保険制度と民間の 医療保険に大別されますが、民間の医療保険には保険期間や内容・対象により、多様な保険商品の区分が存在しています。どのような医療保険に入ればよいのか分からず、悩んでいる方も多いでしょう。
この記事では、医療保険の種類について、保険期間別/内容・対象別に7種類に分けて解説します。民間の医療保険に加入するかどうかで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
1.医療保険の種類
医療保険には、公的医療保険制度と民間の医療保険の2種類があります。
公的医療保険制度は社会保険制度の1つであり、社会政策の一環として国や地方自治体が運営するものです。一方、民間の医療保険は保険会社が提供する保険商品であり、加入者がお金を出し合うことで傷病時の経済的負担を補填する仕組みとなっています。
| 公的医療保険制度 | 民間の医療保険 | |
|---|---|---|
| 加入義務 | 法令による強制加入 | 個人判断による任意加入 |
| 加入目的 | 国民生活の安定 | 公的保障でカバーできない部分への備え |
| 運営主体 | 国・自治体など | 民間企業 |
| 加入審査 | なし | あり |
上記一覧の通り、公的医療保険制度は法令によって加入が義務付けられた医療保険であり、民間の医療保険は個人判断によって任意で加入する点が大きな違いです。
ここでは、それぞれの医療保険の詳細について分かりやすく解説します。
1-1.公的医療保険制度
日本では、国民皆保険制度によって国民全員が公的医療保険制度への加入を義務付けられており、ケガや病気になった際に医療費を支え合うことが可能になっています。
公的医療保険制度の主な種類は以下の3つです。
| 被用者保険 | 会社員や公務員などの被用者とその扶養家族が加入するタイプの健康保険制度です。被用者保険は企業の規模などに応じて健康保険組合・共済組合・協会けんぽの3つに分類されます。 |
|---|---|
| 後期高齢者医療制度 | 原則75歳以上の方が加入することになります。 |
| 国民健康保険 | 被用者保険に加入していない75歳未満のすべての方が加入する公的医療保険です。主に自営業やパート・アルバイトの方などが対象になります。 |
医療費負担が高額になった場合は高額療養費制度を利用することにより、医療費自己負担額は収入に応じて定められた上限額までとなります。
出典:厚生労働省ホームページ
1-2.民間の医療保険
民間の医療保険は、公的医療保険制度ではカバーできない費用を補填する目的で加入するのが一般的です。
公的医療保険制度は医療にかかわるすべての費用を対象としているわけではなく、入院期間に発生した差額ベッド代や食費などの諸費用は自己負担となります。民間の医療保険に加入することで、発生した自己負担費用をカバーすることが可能です。
また、医療費の中でも先進医療にかかる技術料は公的医療保険制度の対象外となり、全額自己負担になります。しかし、民間の医療保険に加入していれば先進医療にかかる費用をまかなえ、経済的な負担を抑えられる点が大きなメリットです。
金銭面の不安が軽減されれば、傷病の治療に関する選択肢も広がるでしょう。
2.【保険期間別】医療保険の種類
民間の医療保険は、保険期間の長さによって「定期医療保険」と「終身医療保険」の2種類に分類されます。医療保険を検討する際には、医療保険の種類ごとの特徴を理解した上で、自分に合った保険商品を選択することが大切です。
ここでは、それぞれの医療保険の概要や加入するメリット・デメリットについて解説します。
2-1.定期医療保険
定期医療保険は、保険期間が一定期間の医療保険です。
定期医療保険の保険期間は、10年などの一定期間をもって満期を迎える年満了タイプと、年齢により期間を決める歳満了タイプの2種類あります。年満了タイプであれば保険期間の終了後でも更新することで契約を継続できますが、歳満了タイプの場合は更新できない場合もあるため注意が必要です。
定期医療保険の保険料は掛け捨てであり、終身医療保険に比べて保険料負担が小さく設定されている点が大きなメリットとなっています。一方で、定期医療保険は更新時の年齢に応じて保険料が上がるため、加入し続けると結果的に払込保険料の総額が終身医療保険より高くなるケースもあります。
2-2.終身医療保険
終身医療保険は、契約時に決めた保障内容が同じ保険料で一生涯続く医療保険です。
終身医療保険の保険料払込方法には、生涯保険料を払い込む終身払いと、一定の年齢で支払いを終える有期払いがあります。終身払いの場合は有期払いに比べて保険料が低く設定されており、経済的な負担を抑えられる点が大きなメリットです。
有期払いは一定の年齢で保険料の払い込みが完了となり、後は保険料を支払うことなく保障を継続できるメリットがあります。いずれにせよ、同じ保障内容を一生涯継続できる点が、終身医療保険のメリットです。
一方、終身医療保険に長く加入していると、段々と自分に合った保障内容でなくなる可能性がある点がデメリットです。
3.【内容・対象別】医療保険の種類
医療保険は、保険の対象者や保険の内容によっても種類が分かれています。今回紹介するのは以下の5つの医療保険です。
- がん保険
- 女性医療保険
- 子ども医療保険
- 引受基準緩和型医療保険
- 無選択型医療保険
それぞれの概要やメリット・デメリットを紹介するので、保険選びの参考にしてください。
3-1.がん保険
がん保険は、がんへの保障に特化した医療保険です。がんと診断確定された場合やがん治療をする場合などに備える医療保険であり、がんに罹患しても生きていくための保険と言えます。
がん保険は、がんが原因で入院・通院する際はもちろん、がんと診断確定された際や、手術や放射線治療などをした際に給付金や一時金を受け取れる点がメリットです。一方がん保険は保険料が掛け捨てのタイプが一般的であるため、その点をデメリットと感じてがん保険に加入しない方もいます。
3-2.女性医療保険
女性医療保険は、通常の医療保険と女性特有の病気に関する特約がセットになった医療保険です。女性特有の病気としては主に以下のものが挙げられます。
- 乳がん
- 子宮がん
- 子宮筋腫、子宮内膜症
- 出産時の帝王切開
- 妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)
女性医療保険は女性がかかりやすい病気に関する保障が手厚いため、女性にとってはメリットのある保険です。女性医療保険に加入していれば女性特有の病気で入院した際、入院給付金に一定額上乗せされるケースもあります。
一方、通常の医療保険と比べて保険料負担が大きくなりやすい点が女性医療保険のデメリットと言えるでしょう。
3-3.子ども医療保険
子ども医療保険は、子どもの傷病に備えるための医療保険です。
子ども医療保険は保障内容が子どもにとって必要なものに絞られており、通常の医療保険に比べてシンプルである点がメリットの1つと言えます。また、一般的には子どもがケガで通院した際にも給付金を受け取れる点も特徴的です。
ただし、小学校入学前の子どもは医療費自己負担割合が2割で済みます。また、地方自治体の助成制度を利用すれば、子どもが入院した場合でも医療機関での窓口負担額を抑えることが可能です。子ども医療保険への加入を検討する際には、その必要性を慎重に考えたほうがよいでしょう。
3-4.引受基準緩和型医療保険
引受基準緩和型医療保険は、通常の医療保険よりも加入時の条件を緩和した医療保険です。健康告知の項目が3〜5個のみであるため、持病や入院歴があるなど、健康に不安がある方でも加入しやすくなっています。
通常の医療保険と比較して告知書がシンプルであり、加入時の煩わしさが緩和されている点も、引受基準緩和型医療保険のメリットの1つと言えるでしょう。ただし、通常の医療保険よりも加入しやすい分、保険料が割高である点は引受基準緩和型医療保険のデメリットです。また、契約後の一定期間は保障対象外になるなどの条件付きのケースもあるため、加入の際にはよく確認する必要があります。
3-5.無選択型医療保険
通常の医療保険は、加入の際に健康状態の告知が必要です。一方、無選択型医療保険は加入の際に健康状態を告知する必要がありません。一定年齢であれば、入院歴・手術歴がある方でも加入できる医療保険です。引受基準緩和型医療保険よりもさらに加入しやすい医療保険と言えます。
無選択型医療保険は、健康上の理由で通常の医療保険などに加入できない方でも加入申し込みができる点が大きなメリットです。ただし、加入前からの傷病については給付制度の対象外である点や、ほかの医療保険に比べて保険料負担が大きい点には注意する必要があります。
まとめ
民間の医療保険の種類は多様です。民間の医療保険は公的医療保険制度を補う存在で、より充実した保障・より充実した医療を希望する方のニーズに応えるものです。
民間の医療保険は保険期間別/内容・対象別に、さまざまなものがあります。保険期間別には、定期型医療保険・終身型医療保険が存在します。内容・対象別には多種多様な保険商品があり、各自のニーズに応じて適切なものを選ぶことが可能です。
自分自身や家族にはどのようなニーズがあるのか、じっくりと検討して適切な医療保険を選びましょう。