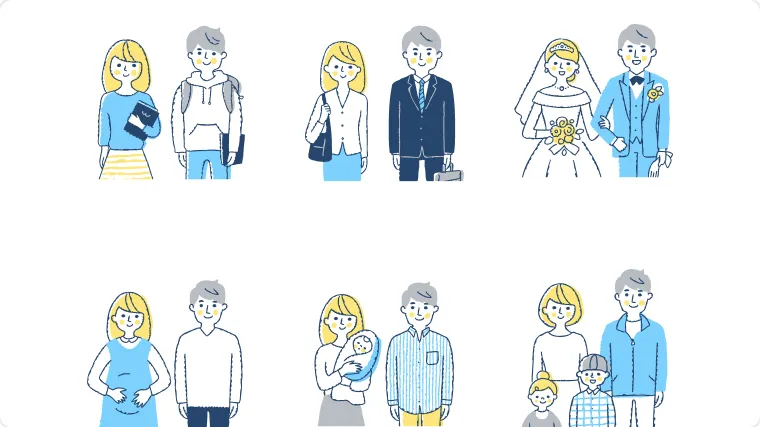
結婚や出産、住宅購入など、人生の大きな節目を迎えるたびに、「保険はどう選べばいいのだろう」と迷う方も多いでしょう。保険には多くの種類があり、専門用語も複雑で、自分に最適な商品を選ぶのは簡単ではありません。保険会社や営業担当者の説明を聞いても、「本当にこの内容で大丈夫だろうか」「不要な保障が含まれていないか」と不安に感じることもあるかもしれません。
この記事では、各年代(20代・30代・40代)で必要となる保険の種類と、ご自身の状況に合った最適な保険の選び方、さらに加入後の見直しのタイミングについて、わかりやすく解説します。
目次
20代・30代・40代のライフステージごとの保険の必要性
保険の必要性は、年齢を重ねるごとに、また家族構成や生活環境の変化とともに大きく変わっていきます。例えば、社会人になったばかりの独身時代は、自分自身のもしもの病気やケガに備える「医療保険」や、病気やケガ で働けなくなった場合に収入を補償する「就業不能保険」が主な検討対象になります。しかし、結婚して配偶者を得たり、子どもが生まれたりすると、ご自身だけでなく、遺された家族の生活を守るための「死亡保障」の重要性が増します。
また、住宅ローンを組んだ場合は、団体信用生命保険(団信)の加入によって死亡保障が一部カバーされるため、生命保険の見直しが必要になることもあります。このように、ライフステージが進むにつれて「誰を守りたいか」「何に備えたいか」という目的が変わるため、それに合わせて保険の内容も柔軟に変えていくことが大切です。
20代の保険選び:医療保障と将来への備え
20代は社会人として経済的な自立を始める大切な時期です。多くの場合、独身か結婚したばかりで子どもがいないケースも 多いでしょう。この時期は、将来の資産形成を考えつつも、まずは「自分自身」に万が一のことがあった場合に備えて 準備をすることが重要です。
医療保険とがん保険の重要性
20代は健康な人が多いため、病気のリスクは低いと感じるかもしれませんが、実は若いうちから医療保険やがん保険に加入しておくことは非常に重要です。
理由は主に2つあります。1つ目は、保険料が割安に設定されている点です。
保険料は、加入時の年齢や健康状態によって決まります。20代は病気や入院のリスクが低いため、保険会社の支払いリスクも小さく、結果として保険料が安く設定されています。
若いうちに加入すれば、保険料を抑えたまま長期間保障を続けられるため、費用対効果も高まります。
2つ目は、一度病気を患うと新たな保険に加入しづらくなったり、保険料が高くなったりするリスクがあるためです。
20代でもがんを含む病気にかかるリスクはゼロではなく、治療費も高額になることがあります。抗がん剤治療が長期化すれば、自己負担額が数十万円に上る場合 もあるため、経済的不安なく治療に専念できる環境を整えることが大切です。
入院や医療費に備えるための保険商品
医療保険では、入院給付金日額や手術給付金の保障内容が重要です。入院給付金は病気やケガで入院した場合に日額で支払われ、一般的には5,000円から10,000円が目安です。手術給付金は所定の手術を受けた際に一時金として支払われるもので、入院給付金の10倍や20倍といった金額が設定されることが多いです。
これらの給付金は、治療費だけでなく入院中の食事代や差額ベッド代、交通費など公的医療保険だけではカバーできない費用の補填にもなります。自身の生活費や貯蓄額を考え、「入院時にどのくらいの金額があれば安心か」という視点で保障額を決めることが重要です。
就業不能保障保険の検討ポイント
20代の方にとって、就業不能保障保険は、医療保険やがん保険と並んで重要な保険です。
なぜなら、多くの場合、20代は自分の収入が唯一の生活基盤であり、病気やケガで長期間働けなくなると、たちまち収入が途絶え、生活に大きな支障をきたす可能性があるからです。
就業不能保障保険を選ぶ際のポイントの一つは、「就業不能」の定義です。
保険会社によって、「全ての業務に従事できない状態」と厳しく定義される場合もあれば、「所定の業務に従事できない状態」と比較的緩やかに定義される場合もあります。
前者は、入院中や医師の指示による在宅療養など、どんな仕事もできないほどの重い状態を指すことが多いです。
一方後者は、現在の職種や職務を続けられない状態を指し、より軽度でも給付対象となることがあります。
また、精神疾患など一部の病気が対象外となる場合もあるため、給付条件を事前に確認しておくことが大切です。
付金が支払われ始めるまでの「支払い対象外期間(免責期間)」も重要な確認ポイントです。
一般的には60日や180日といった期間が設定されており、この期間中は給付金が支払われません。ご自身の貯蓄でまかなえる期間と照らし合わせ、無理のない期間設定を選ぶことが大切です。
受け取れる給付金額は、ご自身の月収や毎月の固定費を考慮して設定し、万一の際に生活が破綻しないような保障額を選ぶことが求められます。
30代の保険選び:家族構成と収入に応じた保障
30代は結婚や出産、住宅購入など人生の大きなイベントが増え、家族を守る視点での保障が重要になります。自分だけでなく配偶者や子どもを扶養している場合は、死亡保障の検討が不可欠です。
配偶者や子どもを扶養する場合の死亡保障
30代で配偶者やお子さんがいらっしゃる場合、生命保険の最も重要な役割の一つである「万一のときの家族の生活保障」について真剣に考える必要があります。ご自身に万一のことがあった際、残されたご家族が経済的に困窮しないよう、適切な死亡保障を準備することが大切です。この保障は、葬儀費用だけでなく、遺されたご家族の生活費、お子さんの教育費、住宅ローンの残債などをカバーするために使われます。
必要な死亡保障額を計算するには、まず「万一の際に残されるご家族が、今後どれくらいの費用を必要とするか」を見積もります。具体的には、お子さんが成人するまでの生活費、大学進学までの教育費、などを合算します。 次に、その総額から、残された配偶者の収入や公的な遺族年金、すでに準備している貯蓄額などを差し引きます。この差し引き後の金額が、不足する保障額、つまり必要となる死亡保険金額の目安になります。
例えば、小さなお子さんがいる家庭であれば、お子さんが自立するまでの期間(約18〜20歳)の生活費や教育費が主な保障の対象となります。このような「一定期間だけ大きな保障が必要」というニーズには、保険料が割安で必要な期間だけ保障を得られる「定期保険」が費用対効果の高い選択肢となります。
死亡保障は、ご家族の将来を左右する重要な要素です。漠然と「いくらあれば足りるだろう」と考えるのではなく、具体的な数字に基づいて必要な保障額を算出し、最適な保険商品を選びましょう。保険会社や保険代理店では、こうした試算をサポートしてくれるサービスも提供しています。
医療保障と就業不能保険の必要性
30代になると、20代と比べて病気やケガのリスクが高まる傾向があり、入院や手術がより必要になるケースも見られるようになります。 特に家計を支える立場にある方にとっては、医療費の負担や長期的な収入減に備えるために、医療保険や就業不能保険の新規加入または 見直しを検討することが重要になるかもしれません。
就業不能保険は、自営業や傷病手当金が短期間しか出ない場合 、住宅ローンや教育費などの固定支出が多い場合に特に重要です。※
※傷病手当金とは、会社員や公務員が病気やケガで働けなくなった際に、健康保険から最長1年6か月間支給される所得補償の制度です。
加入している保険が現在の収入や支出に見合っているか、保障額や免責期間の見直しを検討しましょう。
保険料と保険金のバランスを考慮する
30代は収入が増える一方、住宅ローンや教育費などの支出も増えるため、保険料が家計を圧迫しないようにすることが重要です。無理のない保険料設定を心がけ、保障の優先順位をつけることがポイントです。例えば、貯蓄性のない定期保険を活用し、医療保障も公的制度でカバーできない部分に絞るなど工夫しましょう。
また、教育資金の準備を兼ねて学資保険や貯蓄型の死亡保険を活用するケースもあります。
40代以降の保険選び:老後と健康リスクへの対応
40代は子どもの教育費がピークを迎え、住宅ローンの返済も続く一方、老後資金の準備も意識し始める時期です。このため、保障の見直しと同時に将来に向けた資産形成を意識した保険設計が求められます。
終身保険と定期保険の選択肢
40代以降 の保険選びでは、死亡保障として終身保険と定期保険のどちらを選ぶかが重要です。定期保険は保険料が割安で期間限定の大きな保障に適しており、終身保険は一生涯の保障と貯蓄性を持ち、葬儀費用や老後資金など幅広い目的に活用できます。選択はライフプランや経済状況、保障の目的によって異なり、例えば50代、60代となるなかで子どもが独立したり、住宅ローンを完済したりすると、少額の終身保険で葬儀費用などを準備することも可能です。
がん保険や介護保険の重要性
40代以降 は、がんや生活習慣病などのリスクが高まります。 医療保険はこれらの疾病を重点的にカバーする商品などを検討しましょう。また、介護保険の加入も視野に入れることで、将来の介護費用への備えが可能です。
がんや介護は、一度発症・発生すると長期にわたり多額の費用がかかる可能性があるため、早期に備えを検討することが賢明です。がん保険も例によらず健康状態によっては加入が難しく なることもあるため、ご自身の健康状態が良い時期に検討することをおすすめします。
保険選びの基本:保障内容と保険期間を確認する
これまでライフステージごとに必要な保障について見てきましたが、ここからは具体的な保険の選び方について掘り下げていきます。保険選びの基本は、「誰が、いつまで、いくらの保障を必要とするのか」を明確にすることです。つまり、「保障内容」と「保険期間」の確認が、すべての保険選びの出発点になります。
生命保険を選ぶ際には、ご自身の家族構成や将来の生活設計に基づいて、必要な保障が必要な期間、適切にカバーされているかを確認することが何よりも重要です。漠然とした不安から多すぎる保険に加入したり、逆にいざという時に足りなかったりすることがないよう、一つずつ丁寧に考えていきましょう。
保険料と給付金の適切な設定
保険に加入するにあたり、最も気になることの一つが「保険料」ではないでしょうか。しかし、保険料の安さだけで選んでしまうと、いざという時に十分な保険金・給付金が受け取れず、後悔することになりかねません。
保険商品を決定する際には、ご自身の家族の保障ニーズ、保険金の必要となる期間、そして実際に受け取れる保険金や給付金の額、さらに毎月無理なく支払える保険料の払込期間と金額のバランスを総合的に判断することが重要です。これらの要素を適切に設定することで、将来への漠然とした不安を解消し、安心して生活を送ることができるようになります。
保険料の払込期間と金額の計算方法
保険料の払込方法には、短期間で支払いを終える『短期払』と、保障が続く限り支払いを続ける『終身払』があります。それぞれ月々の負担額や総支払額が異なるため、ご自身のライフプランに合った方法を選びましょう。
保険料の設定にあたっては、家計全体に占める割合を意識しながら、無理のない金額で設定することが一般的です。ただし、生活費や貯蓄の状況などを踏まえ、無理なく継続できる金額に調整することが、保障を長く維持するうえで大切だと考えられます。
保障期間と保険金額の選び方
適切な保険期間と保険金額を設定するためには、万一の際に必要となる「必要保障額」を計算することが重要です。これは、将来かかる支出(遺族の生活費、子どもの教育費などの負債、葬儀費用など)から、遺族の収入や準備済みの資産(配偶者の収入、公的年金、預貯金など)を差し引くことで算出されます。この必要保障額は、子どもの成長や住宅ローンの完済など、ライフステージの変化に応じて変動するため、定期的に見直すことが大切です。
保険商品を選ぶ際の注意点
保険商品を選ぶ際には、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、いくつか注意しておきたい点があります。まず最も重要なのが「告知義務」です。保険を契約する際には、現在の健康状態や既往歴、過去の病歴などを保険会社に正しく伝える義務があります。もし告知を怠ったり、虚偽の告知をしたりした場合、いざ保険金を受け取ろうとした際に、保険金・給付金が支払われない可能性や、契約自体が解除されてしまうこともあります。
保険加入時は、パンフレットや重要事項説明書に記載された「免責事由」を必ず確認し、保険金・給付金が支払われないケースを事前に把握することが重要です。また、営業担当者や保険代理店に相談する際は、ご自身のニーズに合っているか、保険料は無理なく支払えるか、支払い条件はどうなっているかなど、疑問点が解消されるまで積極的に質問し、納得した上で契約を結ぶことが大切です。
保険の見直しタイミング:ライフイベントに応じて
保険は一度加入したら終わりではなく、ご自身のライフプランの変化に合わせて定期的に見直すことがとても大切です。結婚や出産、住宅の購入、転職など、人生の節目には必要な保障内容や保険金額も大きく変わることがあります。
このセクションでは、どのようなライフイベントで保険を見直すべきか、具体的なタイミングとそのポイントについて詳しく見ていきましょう。
ライフプランの変化に合わせた見直し
私たちの人生には、さまざまな転機が訪れます。独身でいる期間、結婚して家族が増える期間、子どもが巣立つ期間、そして老後を迎える期間と、家族構成や収入、住まいなどは常に変化していきます。それに伴い、万一の際に必要となる保障内容や金額も変わっていくのが当然です。そのため、保険もまた、こうした変化に合わせて柔軟に見直していくことが、ご自身とご家族にとって最適な保障を維持する鍵となります。
結婚・出産時の保障内容の再検討
結婚や出産は、生命保険、特に死亡保障を見直す上で最も重要なライフイベントです。結婚時には配偶者の生活保障を考慮した死亡保障の検討が必要となり、出産時には、お子さんの教育費も踏まえた大幅な死亡保障額の増額が求められます。必要な保障額は、家族構成やお子さんの教育方針によって大きく変動するため、具体的なシミュレーションを通じて適切な保障額を算出することが重要です。
住宅購入や転職時の保険加入の見直し
住宅購入時には、住宅ローンに付帯する団体信用生命保険(団信)ではローン残高のみがカバーされるため、家族の生活費や教育費のために別途生命保険を検討する必要があります。また、転職は会社の福利厚生や団体保険の内容が変わる可能性があり、保障の「穴」を避けるために既存の保険の見直しや新たな加入を検討する良い機会です。収入変動に応じて保険料の負担能力も変わるため、家計状況と保障内容のバランスを再調整することが重要です。
老後資金準備のための保険選び
40代以降は「老後資金の準備」という視点での保険選びが重要になり、個人年金保険や貯蓄性のある終身保険が選択肢となります。個人年金保険は計画的な老後資金の積立に役立ち、終身保険は解約返戻金を老後資金に充てることも可能ですが、インフレリスクや元本割れのリスク、運用利回りに注意が必要です。バランスの取れた資産形成のためには、保険だけでなくiDeCoやNISAなどの他の金融商品も視野に入れることが大切です。
まとめ
ここまで、年代ごとの保険の選び方や、具体的な商品の特徴、そして保険の見直し時期について見てきました。保険選びに唯一の正解というものはありません。大切なのは、あなたの今のライフステージと将来のライフプラン、そして「万一のときに何を最も守りたいか」という価値観に合った保険を選ぶことです。
この情報が、保険に関する漠然とした不安を解消し、ご自身にとって最適な保険を見つけるための一歩となることを願います。ぜひ、この知識を武器に、自信を持って保険選びを進めてみてください。
公的医療保険との併用で保障を最大化する
保険を検討する上で忘れてはならないのが、日本の公的な社会保障制度の存在です。特に公的医療保険は、病気やケガで病院にかかった場合でも、自己負担は原則3割に抑えられます。さらに、高額療養費制度を利用すれば、ひと月の医療費自己負担額には上限が設けられています。
民間の医療保険やがん保険を考える際は、まず公的医療保険でどこまでカバーされるのかを理解し、その上で不足すると感じる部分だけを補うようにしましょう。過剰な保険加入は家計を圧迫する原因にもなりかねません。公的保障を土台に、ご自身の貯蓄状況や将来の備えと照らし合わせながら、合理的に民間保険を活用することで、コストを抑えつつ最大限の安心を得ることができます。
なお、死亡や就労不能といった万一のリスクに対しても、「遺族年金」や「障害年金」などの公的保障が用意されています。医療だけでなく、これらの制度も含めて全体像を把握しておくと、より無駄のない保険設計が可能になります。
定期的な見直しで安心の保障を維持する
保険は一度加入したら終わりではなく、加入した時点から「見直し」がスタートすると考えてください。結婚や出産、住宅購入、転職といったライフイベントの節目はもちろんのこと、特に大きな変化がなくても、数年に一度は加入している保険の内容が現在の自分と家族の状況に合っているかを確認することが大切です。
ライフステージが進むにつれて、必要とされる保障内容は少しずつ変化していく可能性があります。たとえば、子どもが独立すれば死亡保障の必要額が減ることも考えられますし、健康状態の変化に応じて、医療保険やがん保険の保障を充実させたいと感じることもあるかもしれません。こうした変化に対応するためにも、定期的に保障内容を見直すことで、過不足のない安心を保ちやすくなるといえるでしょう。
保険見直し本舗で相談する
もし、本記事で解説した内容を踏まえて 、自分に最適な保険選びに不安を感じる場合は、保険の専門家である「保険見直し本舗」へ相談することをおすすめします。複数の保険会社の商品を比較検討し、専門家がお客様のライフステージや将来の計画に合わせた最適な保険プランを無料でご提案します。
客観的な視点からのアドバイスは、納得のいく保険選びに役立ち、保険の知識を深めることにも繋がります。あなたのライフプランに寄り添い、自信を持って保険を選択できるようサポートします。


















