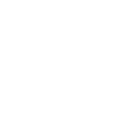「生命保険って本当に必要なの?」「貯蓄や投資で十分じゃないかな?」「加入しても後悔するんじゃないか?」など、生命保険の加入を勧められても、必要性に迷う方は少なくありません。
実は、生命保険は単なる「万が一」の備えだけでなく、家族の生活を守る役割を果たすものです。しかし、条件を確認しないまま加入すると、将来的に後悔する可能性もあります。
そこで本記事では、生命保険の必要性や、加入すべき人の特徴、そして加入しない場合の賢い備え方までを詳しく解説します。「生命保険が本当に自分に必要か」「入るべきか迷っているけど後悔はしたくない…」という方は、ぜひ最後までご一読ください。
目次
生命保険ってそもそも何?
生命保険は、死亡や高度障害といった不測の事態に備えるためのもので、残された家族や本人の生活を経済的に支える役割を果たします。しかし、毎月の保険料負担が重荷に感じられたり、貯蓄や投資で十分な備えができると考えたりすることで「生命保険がいらない」と感じる人も少なくありません。
もちろん、生命保険への加入は法律で義務付けられているわけではありません。
- 生活状況
- 家族構成
- 収入や貯蓄
- 将来の計画
などを総合的に考慮して、判断する必要があります。生命保険が本当に必要かどうかを見極めるためには、自身のライフプランをしっかりと見つめ直し、リスクに対する備えを適切に設計することが重要です。
約8割の人が加入している
生命保険文化センターが実施した2022年度の調査によると、男性の77.6%、女性の81.5%が何らかの形で生命保険に加入しているという結果が出ています。
出典:生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/2022(令和4)年度 リスクに備えるための生活設計生命保険加入率(性別・年齢別)より(https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1221.html)
日本における生命保険の加入率は高い水準にあり、男女ともに50歳代でもっとも加入率が高くなっています。もちろん、統計が示す高い加入率は、必ずしも生命保険が必要であることを意味するわけではありません。
しかし、50歳代からの年代は家族の扶養責任がもっとも重くなる時期であり、同時に自身の老後への備えも意識し始める時期と重なっているためと考えることもできます。こうした傾向を踏まえて、若いうちから将来設計に応じて、生命保険の必要性を慎重に検討しましょう。
生命保険が「いらない」と感じている人の理由とは
生命保険が「いらない」と感じる人が増えている背景には、経済的な要因や価値観の変化があると考えられます。ここからは、生命保険文化センターの行った2018年の調査を踏まえて、生命保険の必要性が低いと感じている人の理由をご紹介します。
経済的に余裕がないから
まず、生命保険へ加入・追加加入意向のない理由の1位は「経済的余裕がない」(52.6%)です。2人に1人は支払う保険料が生活等の負担になることを考え、加入していません。
出典:生命保険文化センター(生命保険に関する全国実態調査〈速報版〉)(https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/30/8QOANJ-h30_zenkoku.pdf)より弊社で作成
また、調査時点の2018年からは、物価高や情勢を踏まえた将来への不安などの変化が後押ししていると考えられます。もちろん、政府により賃上げの動きは強まっていますが、多くの人がこれまでの暮らしの維持に追われやすい状況に当てはまる可能性は依然として高いです。
このことから、できるだけ出費を減らすために、生命保険はまだ「いらない」と判断してしまうと考えられます。
必要性を感じていないから
次に、2018年の生命保険に非加入理由の2位が「現時点では生命保険の必要性をあまり感じない」(25.6%)となっており、前回調査(2015年)から5.8ポイント増加している傾向も読み取れます。単純に、貯蓄や公的保障があればよいと考えて、「いらない」と考える人もいるでしょう。
出典:生命保険文化センター 生命保険に関する全国実態調査〈速報版〉〈図表Ⅱ−40〉 生命保険に関する知識の表(https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/30/8QOANJ-h30_zenkoku.pdf)より弊社で作成
一方で、同調査で行われた知識全般について知識があるかを聞いた別の結果では、66.6%が「生命保険についてほとんど知識がない」との回答もありました。そのため、生命保険の役割や重要性が十分に理解されていないことが、必要性を感じない要因になっているともいえるでしょう。
別の貯蓄のほうが良いから
先ほど掲載した生命保険の非加入理由では、「ほかの貯蓄方法のほうが有利」が前回調査から4.4ポイント増加していました。保険のなかには、万が一のときに備えながら、将来に備えて貯蓄できる『貯蓄型保険』もあります。
貯蓄型保険よりも、例えば投資信託や株式投資など、他の金融商品への関心が高まっている傾向となっていると考えられます。また、単純に保険で貯蓄しなくても、自分で貯金しておきたいという人も一定数いるでしょう。
公的保障だけで十分だから
最後に、社会保障制度への期待が高まる一方で、私的保障としての生命保険の必要性が相対的に低下している可能性もあります。
同調査では「生活保障は公的保障だけで十分」という考え方が16.1%と、前回調査の13.2%から2.9ポイント増加しています。公的保障を充実させるべきという意見も28.5%(前回28.4%)でした。
生命保険等を含めた私的保障を充実してほしいという意見もある一方で、こうした社会的な支援を求める意見もあります。
ここまで触れた理由はそれぞれが単独ではなく、複合的に作用して生命保険が「いらない」と感じる人が増えていると考えられます。
では、生命保険に入らないとどうなるのでしょうか?次では、デメリットについても紹介します。
出典:生命保険文化センター 生命保険に関する全国実態調査〈速報版〉(https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/30/8QOANJ-h30_zenkoku.pdf)生活保障準備は『公的保障と私的保障の両方が必要』が約8割となっている、〈図表Ⅱ−43〉 生活保障の準備に対する考え方
生命保険に入らないとデメリットはある?
生命保険に入らないという選択肢も確かにありますが、そこにはいくつかのデメリットが潜んでいます。
まず、もっとも大きな問題は、「万が一の際の経済的な保障がないこと」です。突然の事故や病気で働けなくなった場合、または不幸にも亡くなってしまった場合、残された家族の生活を支える資金が不足する可能性もあります。
また、生命保険には死亡保障以外にも、医療保障や介護保障などの特約が付けられることも多いです。この保障がないと、長期入院や介護が必要になった際に、高額な医療費や介護費用を自己負担で賄わなければならなくなり、家計の負担になるかもしれません。
生命保険に加入するかどうかの判断は、個人の状況によって異なります。
自分に本当に必要な保障は何か?どの程度の保障があればいいのかわからない…等と迷ったときは一度専門家のアドバイスを受けてみるのもおすすめです。
生命保険に入るべき人はこんな人
生命保険の必要性は、個人のライフステージや家族構成、経済状況によって異なります。
その上で、
- 扶養家族がいる人
- 十分な貯蓄がない人
- 将来の経済的リスクに備えたい人
などに当てはまる方は生命保険に加入しておくとよいでしょう。
ここでは、生命保険が特に重要となることが多い人のケースについて詳しく見ていきましょう。
独身の場合
- 長期入院や高額治療のリスクを懸念する人
- 公的医療保険の補完を考えている人
- 将来の結婚・出産を考えている人
独身者にとって、生命保険、特に死亡保険の必要性は比較的低いと言えます。扶養家族がいない場合、自分の死後に経済的支援を必要とする人がいないためです。
しかし、将来の結婚や出産を考えている場合は、若いうちに加入することで保険料を最適化できる可能性があります。
また、病気やケガに備える医療保険は、長期入院や治療費以外でかかる費用(食事代や日用品など)や働けない間の収入を考えて検討しましょう。
共働き夫婦の場合
- 住宅ローンなどの負債がある人
- 子育て期間中など経済的リスクが高い時期の人
- 一定期間の保障で十分な人
- 子育て期間中の経済的保障を必要とする夫婦
共働き夫婦の場合、お互いに収入があるため、一方が亡くなっても残された配偶者の収入で生活を維持できることが多く、死亡保険の必要性は比較的低いと言えます。
しかし、住宅ローンなどの負債がある場合、子育て中で経済的に不安がある場合などは、将来のリスクを踏まえて検討してもよいかもしれません。また、収入保障保険など、必要な期間だけ保障される保険も選択肢として考えられます。
子どもがいる家庭の場合
- 主たる収入源である人
- 小さい子どもがいる人
- 子どもの独立までの期間、保障が必要な人
- 子どもの教育費確保を考えている人
子どもが小さい家庭では、死亡保険の必要性が他のケースと比べて高くなります。また、主たる収入源である親が亡くなった場合、残された家族の生活費や子どもの教育費をカバーする必要があります。
この場合、定期保険や収入保障保険など、保障期間を子どもの独立に合わせて検討しましょう。必要な期間中は十分な保障を得つつ、子どもが独立した後は保険料負担を減らすことができます。
高齢者の場合
- 長期入院のリスクを懸念する人
- 将来の介護に備えたい人
- 葬儀費用の準備を考えている人
- 遺族の経済的負担を軽減したい人
高齢者にとって、死亡保険の必要性は一般的に低くなります。代わりに、高齢になるほど長期の入院や介護が必要となるリスクが高まるため、医療保険や介護保険など、病気や介護に備える保険の必要性が高まります。
また、葬儀費用を準備するために、少額の死亡保険に加入するのも1つの選択肢です。遺族の経済的負担を軽減できるか、自身の健康状態と将来の介護ニーズはどうなるかを考慮しましょう。
やめたら後悔する?生命保険が不要になって解約する際の注意点
「生命保険はいらない」と思っていても、解約する際にはデメリットを十分に理解し、自身の状況を冷静に分析することが重要です。ここでは、生命保険の解約に関する重要な注意点を3つ見ていきましょう。
解約返戻金が元本割れする可能性がある
生命保険を解約する際に受け取れる金額、つまり解約返戻金は、契約内容や解約時期によって変動します。特に注意が必要なのは、加入してから間もない時期の解約です。この場合、払い込んだ保険料の総額よりも少ない金額しか戻ってこない、いわゆる元本割れのリスクが高くなります。
加入後すぐに「生命保険はいらない」と判断し、解約に至らないように、最初から目的に応じた保障内容と無理のない保険料で設定しましょう。求める保障の過不足はないか、解約前に見直すのも1つの方法です。
再加入できなくなる・保険料が高くなる
生命保険を解約後に健康状態が悪化した場合、再加入が困難になったり、保険料が高くなる可能性もあります。保険会社は加入時の健康状態を厳しくチェックするため、以前は問題ない保険商品でも、加入を認められないことがあります。
また、一般的に保険料は年齢の上昇と同時に高くなるものです。「いらない」と思って若いうちに解約し、後になって必要性を感じて再加入しようとすると、想定以上の保険料に戸惑うかもしれません。生命保険の解約を検討する際は、解約前に「不要な保障を減らすことはできないか」をまず考えましょう。
代替手段を見つけておく必要がある
繰り返しお伝えしていますが、生命保険の解約を考える前に、まずは現在の契約内容の見直しで対応できないかを考えます。「生命保険はいらない」と思っても、完全に解約してしまうのではなく、自分のニーズに合わせた調整をおこなうことで求める保障を受けつつ、保険料を最適化できる可能性もあります。
保険商品は解約以外にも、払済保険への変更、特約の見直しなど、さまざまな選択肢があります。
家計の状況や将来の計画を踏まえて、自分に最適な保障がなにか知りたい方はまずは専門家へ相談してみましょう。保険見直し本舗では無料で相談を受け付けているため、ぜひお気軽にご利用ください。
生命保険に入らない場合の賢い3つのお金の備え方
生命保険に入らないと決めた場合でも、人生には予期せぬ出来事が起こるものです。そのため、生命保険の代替として考えられる3つの賢明な備え方を紹介します。
貯蓄
貯蓄は、万が一の事態に備えて、最低でも生活費の3〜6か月分の現金を目安に緊急時の資金源を確保しましょう。突然の収入減少や予期せぬ出費に対する備えになります。
計画的な貯蓄をおこなうには、まず目標金額を設定し、毎月の収入の一定割合(例えば10〜20%)を貯蓄に回すことが効果的です。自動振り込みを設定するなど、継続的な貯蓄習慣を身につけるとよいでしょう。
投資
投資は、長期的な視点で資産を増やすための手段です。ただし、投資にはリスクが伴うため、自身のリスク許容度を理解し、適切な投資戦略を立てることが重要です。例えば、分散投資は、
- 株式
- 債券
- 不動産投資信託(REIT)
などを組み合わせることで、いずれかの価値が下落した際にリスクを分散できます。また、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの制度を活用する方法も挙げられます。
関連記事:NISAで始める投資の一歩
公的保障
公的保障制度は、生命保険に入らない場合でも国民健康保険や国民年金などを利用できる制度です。例えば、下記のようなものが挙げられます。
- 傷病手当金
- 入院時食事療養費・入院時生活療養費
- 療養費
- 訪問看護療養費
公的保障制度は複雑で分かりにくい面もありますが、自分や家族が利用できる制度を事前に確認し、理解しておくことが大切です。
まとめ
生命保険は、約8割の日本人が加入している一方で、経済的な理由や必要性を感じないことから「いらない」と判断する人も少なくありません。独身者や共働き夫婦、高齢者など、それぞれの状況に応じて必要性を慎重に判断しましょう。
また、現在加入している生命保険の解約を検討する際は、解約返戻金の元本割れや再加入が難しくなるケースがあるなど、デメリットを踏まえた上でまずは「見直し」することをおすすめします。
経済的な備えとなる生命保険は一度決めたら終わりではなく、定期的に見直し、調整することが安心の保障を無理なく継続するコツです。自分に本当に必要な保障は何か、どの程度の保障が適切なのかなどで迷ったら、専門家のアドバイスを受けてみましょう。
よくある質問(FAQ)
生命保険に入っていないとどうなる?
生命保険に加入していない場合、万が一の事態に備えが足りなくなる可能性があります。主な目的は、残された家族の生活を守ることですが、それだけではありません。
金融資産としての側面もあり、例えば解約返戻金や契約者貸付などの機能を活用することで、急な出費にも対応できることもあります。
詳しくはこちら:9割の世帯が加入する死亡保険(生命保険)は本当に必要か?
医療保険がいらない貯金額は?
医療保険が不要となる貯金額の目安としては、約2,400万円とされています。2010年の厚生労働省の調査結果で、生涯にわたる医療費の平均を目安として考えた場合です。
ただし、これは1つの目安にはなりますが、あくまで平均値であり、個人の健康状態や家族構成、生活スタイルによって必要な金額は変わってきます。
出典:厚生労働省(生涯医療費)(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/shougai_h22.pdf)
生命保険に入らない人の割合は?
生命保険文化センターが2022年度に実施した「生活保障に関する調査」によると、生命保険の加入率は男性で77.6%、女性で81.5%となっています。
つまり、生命保険に加入していない人の割合は、男性で約22%、女性で約18%ということになります。ただし、この統計には個人年金保険やグループ保険、財形貯蓄などは含まれていません。
出典:生命保険文化センター(リスクに備えるための生活設計)(https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1221.html)